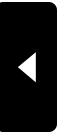2015年09月16日
水害家屋の補修例
先日の大雨による川の氾濫のニュース映像を見る度、4年半前の記憶がフラッシュバックしてきます。
被害に遭われた方が自宅へ戻り、変わり果てた自宅を前に立ちつくす様子を見て自分の事の様に胸が苦しくなりました。
まだ水がひかずに家に辿り着けない方もおられるようで、心配で仕方ないと思います。
何処から手をつけたら良いのか途方にくれる光景・・・
必死にドロだし作業をする光景・・・
我が家も4年半前に津波で同様の経験をしました。
その時の経験を思い出し、家の補修に至るまでの工程をここに残してみようと思います。
まず、手をつける前に記録写真を撮りましょう!
※後日、保険請求や支援金を受け取る為に必要になります。
※震災の時は写真を撮らずに補修してしまった結果、何の補償も受けることが出来なかった方もおられます。
被害に遭われた方が自宅へ戻り、変わり果てた自宅を前に立ちつくす様子を見て自分の事の様に胸が苦しくなりました。
まだ水がひかずに家に辿り着けない方もおられるようで、心配で仕方ないと思います。
何処から手をつけたら良いのか途方にくれる光景・・・
必死にドロだし作業をする光景・・・
我が家も4年半前に津波で同様の経験をしました。
その時の経験を思い出し、家の補修に至るまでの工程をここに残してみようと思います。
まず、手をつける前に記録写真を撮りましょう!
※後日、保険請求や支援金を受け取る為に必要になります。
※震災の時は写真を撮らずに補修してしまった結果、何の補償も受けることが出来なかった方もおられます。
まずは瓦礫片付け&泥出しになりますが、床の上に乗ったヘドロがとても滑りやすく危険だった為水没したカーペットなどを切り通路になる床の上に敷き詰めました。(滑って骨折した知り合いも・・・)
我が家は床上1mほどの浸水被害でしたので、泥出し作業と平行して捨てるものと残すものの仕分けをしながらでした。
毎日ただただ無心で泥出し作業をする日々でしたが、ヘドロまみれになった子供達のオモチャを捨てる時がとても切なかったです。
その後は家の中を水洗い。。。

まさか家の中をデッキブラシで水洗いする日が来るとは思いませんでしたね。。。
とはいっても家屋にとってはあまり良いものではないので、できるだけ短時間で洗い、
しっかりと水気をふき取って早めに乾燥させるように勤めました。
一ヶ月後、待ちに待った業者さんの手によって床を開けてもらい、床下のヘドロ出し作業

半分乾いたヘドロの下は乾きにくい海水の滲みこんだ土でした。
その為、ヘドロが滲みこんだ土を自分達でさらに多めに削り取りました。

床下のドロ出しには写真に写ってる様な“ちりとり”が便利でした。
(スコップだと小回りが利かないので、ちりとりとシャベルなどで集め、バケツなどに移し運搬する感じで)
そうそう、水没した引き出しは水を吸って引き出す事が出来ず・・・
引き出せる上の方から底を切り抜いて中に残っている海水を抜いたのでした。

こんなところにまでもれなく行き渡ったヘドロ・・・。
その後、水没していない部分などにビニールで養成をし高圧洗浄機で洗浄。

そして、消毒の為に希釈したベンザルコニウム塩化物液を噴霧器で隅々まで噴霧しました。
噴霧器が無い場合はバケツに入れた希釈液を雑巾に含ませ拭きあげをしても効果がある様です。
食器などの小物は希釈液に漬け置きにしたり、ふきんで拭いたり。
いくら洗っても綺麗になった感覚のなかった壁や床も乾いた後はサラサラとした肌触りになり
目に見えない雑菌まみれになった家の中がスッキリした様に感じました。
汚水まみれになった家の中、小さい子供がいる家庭では消毒面が特に気になる所だと思います。
我が家も当時は2歳と6歳でしたので、消毒面はかなり気を使いました。

お風呂は再使用ということで納得いくまで何度も何度も洗い消毒をしました。
床下の話に戻りますが、柱等の消毒はベンザルコニウム塩化物液で済みましたが、
海水と重油の滲みこんだ土・・・これの消毒には消石灰を使いました。

柄杓で隅々まで撒いた後、レーキで撹拌しました。
そして湿気が上がってこないようにその上に農業用の厚手のビニールを敷き詰め川砂を重しにして固定。
(この作業をする時点で充分に乾燥させてはいましたが、海水を含んでいる為か湿気を帯びていました)
そして脱臭の為にネットに入れた木炭を置きました。

と、ここまで自分達でやった上で、業者さんに来てもらい基礎の補修&補強から見直してもらい本職による工事がスタートしました。

津波から3が月半が経ち畳が入ってはしゃいでいた子供達の姿が今でも目に焼きついています。。。
それからもうひとつ!
柱や壁、建具などへ重油が滲み込み変色していたのですが、
建具屋さんが使っていたこの“レブライト”のシミ抜き効果が良かったので、別途購入して柱や壁のシミに使いました。


取り扱い注意の業務用ですので注意が必要ですが。

面白いように綺麗になると喜んだ親父は築30数年のシミや汚れを徹底的に落としていました。
レブライトの安全タイプで“シミトップ”というのもある様です。
淡水と海水の違いはあれども
氾濫した川の水も津波も同じ汚水
下水や糞尿、工業排水、堆肥、科学薬品・・・etc
何が入っているかも分からない泥水です。
チリ地震津波など過去の津波を経験した地区では「津波を被った物はすべて処分しなきゃだめだ」と言い伝えられてきたそうです。
しかし、昔と違い消毒剤も沢山存在していますので、有効に使えば再使用できる物が増えるかもしれません。
震災当時、津波被害家屋の処理方法についての情報は少なく、業者もかなりの順番待ちという状況でしたので各家で自分達なりに考えて行っていました。
この記事はその一施工例です。
私は建築関係の専門家ではありませんので間違いもあるかもしれませんが・・・
今、調べてみると業者さんも同じような処理をしている様です。
床上に少しあがっただけだから・・・と床下の処理をしなかった知り合いは後になってカビが発生したりして再工事する事になった家もありました。
今回、被害に遭われた方の目に留まって少しでも参考になればよいのですが・・・
被害に遭われた方々の生活がはやく元に戻れるよう心からお祈りいたします。

にほんブログ村
我が家は床上1mほどの浸水被害でしたので、泥出し作業と平行して捨てるものと残すものの仕分けをしながらでした。
毎日ただただ無心で泥出し作業をする日々でしたが、ヘドロまみれになった子供達のオモチャを捨てる時がとても切なかったです。
その後は家の中を水洗い。。。

まさか家の中をデッキブラシで水洗いする日が来るとは思いませんでしたね。。。
とはいっても家屋にとってはあまり良いものではないので、できるだけ短時間で洗い、
しっかりと水気をふき取って早めに乾燥させるように勤めました。
一ヶ月後、待ちに待った業者さんの手によって床を開けてもらい、床下のヘドロ出し作業

半分乾いたヘドロの下は乾きにくい海水の滲みこんだ土でした。
その為、ヘドロが滲みこんだ土を自分達でさらに多めに削り取りました。

床下のドロ出しには写真に写ってる様な“ちりとり”が便利でした。
(スコップだと小回りが利かないので、ちりとりとシャベルなどで集め、バケツなどに移し運搬する感じで)
そうそう、水没した引き出しは水を吸って引き出す事が出来ず・・・
引き出せる上の方から底を切り抜いて中に残っている海水を抜いたのでした。

こんなところにまでもれなく行き渡ったヘドロ・・・。
その後、水没していない部分などにビニールで養成をし高圧洗浄機で洗浄。

そして、消毒の為に希釈したベンザルコニウム塩化物液を噴霧器で隅々まで噴霧しました。
噴霧器が無い場合はバケツに入れた希釈液を雑巾に含ませ拭きあげをしても効果がある様です。
|
|
|
|
食器などの小物は希釈液に漬け置きにしたり、ふきんで拭いたり。
いくら洗っても綺麗になった感覚のなかった壁や床も乾いた後はサラサラとした肌触りになり
目に見えない雑菌まみれになった家の中がスッキリした様に感じました。
汚水まみれになった家の中、小さい子供がいる家庭では消毒面が特に気になる所だと思います。
我が家も当時は2歳と6歳でしたので、消毒面はかなり気を使いました。

お風呂は再使用ということで納得いくまで何度も何度も洗い消毒をしました。
床下の話に戻りますが、柱等の消毒はベンザルコニウム塩化物液で済みましたが、
海水と重油の滲みこんだ土・・・これの消毒には消石灰を使いました。

柄杓で隅々まで撒いた後、レーキで撹拌しました。
そして湿気が上がってこないようにその上に農業用の厚手のビニールを敷き詰め川砂を重しにして固定。
(この作業をする時点で充分に乾燥させてはいましたが、海水を含んでいる為か湿気を帯びていました)
そして脱臭の為にネットに入れた木炭を置きました。

と、ここまで自分達でやった上で、業者さんに来てもらい基礎の補修&補強から見直してもらい本職による工事がスタートしました。

津波から3が月半が経ち畳が入ってはしゃいでいた子供達の姿が今でも目に焼きついています。。。
それからもうひとつ!
柱や壁、建具などへ重油が滲み込み変色していたのですが、
建具屋さんが使っていたこの“レブライト”のシミ抜き効果が良かったので、別途購入して柱や壁のシミに使いました。


取り扱い注意の業務用ですので注意が必要ですが。

面白いように綺麗になると喜んだ親父は築30数年のシミや汚れを徹底的に落としていました。
|
|
|
レブライトの安全タイプで“シミトップ”というのもある様です。
淡水と海水の違いはあれども
氾濫した川の水も津波も同じ汚水
下水や糞尿、工業排水、堆肥、科学薬品・・・etc
何が入っているかも分からない泥水です。
チリ地震津波など過去の津波を経験した地区では「津波を被った物はすべて処分しなきゃだめだ」と言い伝えられてきたそうです。
しかし、昔と違い消毒剤も沢山存在していますので、有効に使えば再使用できる物が増えるかもしれません。
震災当時、津波被害家屋の処理方法についての情報は少なく、業者もかなりの順番待ちという状況でしたので各家で自分達なりに考えて行っていました。
この記事はその一施工例です。
私は建築関係の専門家ではありませんので間違いもあるかもしれませんが・・・
今、調べてみると業者さんも同じような処理をしている様です。
床上に少しあがっただけだから・・・と床下の処理をしなかった知り合いは後になってカビが発生したりして再工事する事になった家もありました。
今回、被害に遭われた方の目に留まって少しでも参考になればよいのですが・・・
被害に遭われた方々の生活がはやく元に戻れるよう心からお祈りいたします。
にほんブログ村
Posted by kick at 07:00│Comments(0)
│◆3.11













![【送料無料】KARCHER(ケルヒャー) K2.200 [高圧洗浄機]](http://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/?pc=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2fa-price%2fcabinet%2fimage%2f111%2f4039784710573.jpg%3f_ex%3d128x128&m=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2fa-price%2fcabinet%2fimage%2f111%2f4039784710573.jpg%3f_ex%3d80x80)